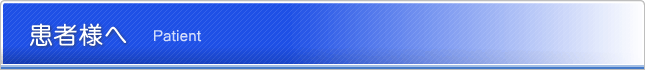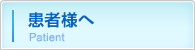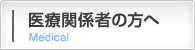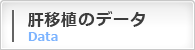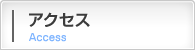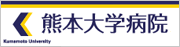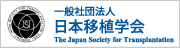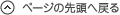肝移植の手引き
2)移植後中長期的合併症
移植後少し日時を経て起こってくる合併症があります。これらには、a) 拒絶反応、b) 免疫抑制の副作用、c) 血管、胆管の吻合部狭窄、d) 肝炎や肝癌、原発性胆汁性肝硬変や原発性硬化性胆管炎などの移植前の病気の再発などがあります。以下、そのそれぞれについて説明します。
a) 拒絶反応と免疫抑制
肝移植を受けたすべてのレシピエントには、拒絶反応を防ぐために、タクロリムス(プログラフ)またはサイクロスポリン(ネオーラル)、ステロイド、ミコフェノール酸モフェチル(セルセプト)などの名前の「免疫抑制剤」を投与する必要があります。これらは免疫力の低下や成長障害、糖尿病、腎障害などの副作用をひきおこすこともある薬剤ですが、移植手術の術後管理にはなくてはならないものです。もしも免疫抑制剤を全く使用しない場合には、拒絶反応はすべてのレシピエントにおこり、その移植肝は早晩壊死に陥ります。免疫抑制剤の主な効果は、移植肝に対する拒絶反応を抑えることですが、この薬剤の投与により、レシピエントは感染症にかかりやすくなります。感染も、レシピエントを取り巻く外界からの感染(伝染)というより、本来レシピエントのみならず多くの人が持っていて体内で共存しているような病原体(細菌、真菌、ウイルスなど)などによる感染症であることがむしろ特徴的です。ただし、この感染にかかりやすい状態は、骨髄移植のような無菌室への隔離を必要とするような状態ほどひどくなく、一般病棟で十分管理可能であり、もちろん退院後通常の生活をおくる上では何の妨げにも成りません。
拒絶反応は、軽いものも含め約40%のレシピエントに生じます。早い場合には術後5日目頃から生じますが、最も多いのは、術後2-3週目ころです。肝移植では、拒絶反応の90%以上は免疫抑制剤の増量によって治療可能であり、免疫抑制剤を適切に使用すれば、移植された肝臓が拒絶反応のために失われる確率は非常に小さくなります。ただ、まれに種々の治療に抵抗して拒絶反応が抑制できない難治性の拒絶反応、あるいは慢性拒絶反応と言われる場合もあり、この場合には、もういちど移植をしないと致命的になる場合があり得ます。
サイクロスポリン、タクロリムス、ステロイド等にもいくつかの副作用があります。このため、できるだけ少ない投与量で有効にお薬を効かすために、血液の中の薬の濃度を測定したりして個々のレシピエントにあった投与量に調節する工夫をします。移植後の入院中には、採血するたびにこの血中濃度の測定を行います。退院後は、外来受診時にチェックするのみとなります。これらの免疫抑制剤は段々減りますが、最終的にはタクロリムス1剤だけの少量投与を一生継続していくことになります。ごく一部のレシピエントでは免疫抑制剤を完全に中止しても肝機能に影響がでず、移植された肝臓が自分のものになった(免疫寛容状態といいます)と判断されるケースが時にありますが、どういう組み合わせだとそうなるのかはまだ不明で、原則的には一生お薬を服用していただくものだ、とご理解ください。
非常に少ない確率ですが、慢性拒絶反応と言って、術後数ヶ月以降に、肝機能が悪化して、特に黄疸が強くなり、通常の拒絶反応の治療が有効でない場合があります。新しい薬も開発されていますが、このような拒絶反応はなかなか制御が難しく、進行して、移植した肝臓の機能が低下し、再移植を考慮せざるを得なくなる場合があります。
b)免疫抑制剤の長期的副作用
主な免疫抑制剤として現在用いられる、タクロリムス、サイクロスポリンは、薬剤としての副作用を持っています。両者に共通する副作用は多く、腎障害、耐糖能異常(血糖が高くなる)、高脂血症、神経系の異常、高血圧、高カリウム血症などがその主なものです。腎障害などは、その薬物の血中濃度の程度に左右されますが、神経系の異常など、あまり血中濃度とは相関しないものもあります。また、長期服用することになる薬ですが、長期間の投与で腎障害や耐糖能異常などが起こってくることもあり、特に術後長い人生を免疫抑制剤とともに生きていく小児では十分注意する必要があります。
タクロリムスが、現在最も多くの肝移植後患者さんが長期間飲み続ける薬です。薬の形には、粉末やカプセルなどの種類があり、薬剤の成分の含有量も0.2mgから1mgまでいろいろです(図24)。
 |
| 図24 免疫抑制剤 プログラフの各種剤型 |
|---|
これによって、その組み合わせでいろいろな服用量を設定することができ、特に、移植後の早期、血液の中のこの薬剤の濃度(血中濃度)を計りながら毎日、服用量を調節するときなどに重宝です。また、薬がうまく飲めない子供さんには粉薬を溶かして飲ませたりも出来ます。タクロリムスは、基本的に1日に朝晩の二回服用する薬ですが、患者さんによっては、1日1回でいい方もおられますし、1日1回の服用でよい徐放性製剤のタクロリムスもあります。また、術後の経過によっては、減らしたりやめたりすることもあり、長期にわたる経過観察でいろいろな経過があります。
c)血管や胆管をつないだ部分が狭くなること(狭窄)
門脈、肝静脈の血管、および胆管では、数ヶ月から2年くらいの間に、移植手術の時につないだ血管や胆管のつなぎ目が細くなってしまうことがあります。胆管が詰まれば黄疸がでたり熱がでたり肝機能が悪化したりします。血管が細くなってその程度が強いと、肝臓の働き自体に重大な影響を与えることがあります。血管の狭窄は、全体の5%以下、胆管の狭窄は約10%の症例にみられます。これらは、日常の術後の経過観察で、症状や血液検査、超音波検査なども含めて診断し、放射線科、あるいは消化器外科などと共に、その治療にあたることになります。具体的には、狭いところがあれば風船を膨らませて広げる、場合によってはもう一度開腹して再手術をする、というような対応が必要になることがあります。よって、診断治療のために、手術から時間がたっているにもかかわらず、何度か入退院を繰り返すようなことになることがあります。種々の治療によって改善できない場合、再移植を考慮せざるを得ない場合もあります。
d)もとの病気の再発
肝移植を必要とするある種の病気、たとえば、B型やC型のウイルス性肝硬変、肝臓癌、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎などでは、移植後もある確率でまた同じ病気が移植された肝臓に生じてしまうことがあります。もちろん、その確率が相当高く、かつ重篤である場合には、肝臓移植そのものが妥当でない(有効でない)わけです。
C型の肝硬変では、もとの病気が再発する可能性は決して小さくなく、またそれが移植肝の機能を大きく損なって機能不全に陥らせ、数ヶ月という早期に再移植以外に救命の道が無くなるという事態も5%程度の確率であり得ます。C型肝炎は、早い場合、移植して1ヶ月程度で肝機能の異常が明らかになり、原因が不明確なため肝生検をしてみると診断が確定することがあります。治療として、リバビリンという飲み薬と、インターフェロンの注射治療を開始します。この場合、消化器内科の専門医とともに診ていくことになります。
また、B型肝炎ウイルスの肝硬変で移植したかたも、何もしないと新しい肝臓に再び肝炎が生じることがあり、抗ウイルス剤と、免疫グロブリンという注射を併用して再発を予防します。B型は、C型より予防策が有効です。また、B型肝炎にかかって今は抗体ができて治っているドナー(既感染ドナー)から、B型肝炎の抗体を持っていないレシピエントに肝臓が移植されると、ドナーの肝臓の中に潜んでいたウイルスが元気になり、レシピエントで新たに肝炎を起こすことがあります。このような場合も、抗HB肝炎ウイルス免疫グロブリンを投与して予防することができます。そのような組み合わせの場合には詳細に説明いたします。
肝臓癌では、ある程度進行した状態ですと肝臓を全部摘出して肝移植をしても、すでに血液の中や体のどこかに目に見えない形で転移していることがあります。移植の前には、頭(脳や頭蓋骨)、胸(肺や肋骨)、腹部のCT、全身の骨のシンチグラムなどの検査で、転移の有無を詳細にしらべ、もし転移が見つかればその時点で移植は中止になります。個々の肝臓癌の進行具合(=移植後再発の可能性)と、たいていはいっしょにある事が多い肝臓の機能障害(=肝不全での死亡可能性)双方を勘案して、移植の効果がどの程度期待できるかが違います。よって個別に口頭で説明いたします。
原発性胆汁性肝硬変や、原発性硬化性胆管炎でも再発の可能性が5-20%の頻度で報告されていますが、再発してもすぐに肝硬変になって移植肝の機能が無くなってしまうようなことは非常に少ないので、あまり過度に心配される必要はないと思います。いずれの疾患でも、その特徴を考えて、免疫抑制剤の使い方などで再発がおこりにくいような対応をとり、治療方法を考えます。